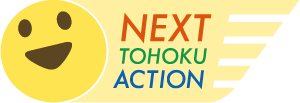西村和紘くん(埼玉県/さいたま市立木崎中学校2年)
地球温暖化が進んでいる中、南相馬ソーラー・アグリパークで行っている自然エネルギーの活用や水耕栽培の現場を見て、これからの未来の在り方を学んだような気がします。小高区では、立ち入りが許可された後でも住民がいない街を歩き、自分が住んでいる街との差に驚き、ショックでした。

中野萌さん(広島県/呉市立広中央中学校3年)
2つの取材先どちらも、人々が協力しあって復興のために頑張っている姿を見ることができ、自分も何か役に立つことができないか、と考えるきっかけになりました。

多田優実花さん(岐阜県/岐阜大学教育学部付属中学校3年)
南相馬ソーラー・アグリパークでは、お年寄りの方が花を植えて前向きに頑張っていたり、相馬野馬追の中島さんから各地に避難した騎馬会員の方々が祭りの通常開催のために努力していたというお話を聞いたりして、人のつながりが素晴らしいものだと感じました。

加賀隼人くん(秋田県/大仙市立太田中学校3年)
南相馬ソーラー・アグリパークでは、太陽光エネルギーと野菜栽培を通じた体験学習が今までにない経験で、とても興味深く感じました。相馬野馬追は中島さんのお話を聞いて、自分もこの歴史あるお祭りを語り継いでいけたらと思いました。

池内勇太くん(徳島県/鳴門市立鳴門中学校3年)
今日、南相馬市の人たちにふれあい、みんな自分にできることを見つけてそれぞれに頑張っている姿を見ることができました。自分も、被災地のために何か役に立てることを考えて行動しなければならないと感じました。





中学生を交えた3回目の取材は福島県南相馬市となりました。
全国から中学生を迎えるにあたり、参加してくれる中学生やそのご両親がどのような思いで福島県にいらっしゃるのか、正直なところでは少し心配な部分もありました。
我々はそこに暮らしている、安全である。でも、外からどう思われているかは分からない・・・。
このプロジェクトは「風評・風化を防ぐ」ことを目的の一つとしていますが、中学生の素直な目で見た、福島の『いま』を伝えて欲しいと思います。
取材後、中学生たちが取り組んでくれている、それぞれの新聞を作る、という作業を楽しみに待っています。いずれ当ホームページでも公開されますので、皆様にもお届けさせていただきます。
今回の取材では、南相馬市役所の復興企画部のご協力を得て、南相馬市小高地区(旧警戒区域)を視察しました。崩れたままの家、閉鎖している学校…中学生にとっては、ショッキングな光景が広がっていたと思います。それが、福島の『いま』なのです。震災報道が減り、全国にこの光景が伝わることはなく、人々は日常生活に戻っていると思います。一方で、手つかずの“崩壊”が2年と半年経つ今でもそのままになっていることを知って頂きたいのです。
人けの無い街、JR東日本常磐線の駅である小高駅は時が止まり、周辺の放置された、放置せざるを得なかった自転車には草が絡んでいます。駅に止まった車の持ち主は、いまどこにいるのでしょうか。
この場所は、皆が見捨て出ていた街ではありません。過疎化の結果でもありません。暮らしたくても暮らせない、戻りたくても戻れない街なのです。今もし、自分の住んでいる街から、突然何も持たず今すぐ出ていかなければならないとなったことを是非想像してみて頂きたいです。財産も、思い出も、何も持たずに。
取材は、福島の代表的なお祭り野間追<伝統>とソーラーパネル事業と言う新しい取組<先端>とを対比する形で並べました。野間追はこれまで、外に開かれたイメージは少ないかも知れません。しかし、多くの支援・励ましを受け、地元の人々自身も変わろうとしているような気がしています。復興しなければいけないのは我々ですが、我々は、我々だけでは復興できません。それは甘えではなく、知っている人がいてくれる、どこかで応援してくれている人がいる、と思うことが支えになる、というレベルです。
一歩一歩前へ、一緒に。
次回は、宮城県名取市の取材の模様をお伝えして行きます。

南相馬市ボランティアセンター -中学生記者 西村くん撮影

©Natsuki YASUDA / studio AFTERMODE